猫による被害にお困りの方へ
東大阪市では「敷地内で糞尿をされて困っている」「近所で野良猫が増えて困っている」「夜中に鳴き声がうるさい」などの苦情や相談が多く寄せられています。
そこで、猫の被害の軽減に比較的効果があると思われる方法をご紹介します。
【注意】
- 個体差もあり、あまり反応しない猫もいるので効果を保証するものではありません。
- 方法によっては効果が長続きしない場合や、反復継続することが必要な場合があり、猫が慣れてしまい反応しなくなる場合もあります。
- ポイントは、猫が「不快な場所」ということを学習するように仕向けることです。
- 猫は愛護動物です。虐待に当たるような行為は法律により罰せられます。
忌避方法のご案内
忌避剤について
- 猫の嫌いな臭いや刺激臭によって猫が近寄りにくくする方法です。
- 雨や風で効果が薄れてしまうので、効力を維持するために定期的に交換する必要があります。
- 臭いが強いものや色が付いてしまうものもあります。あらかじめ、ご近所にも説明しておきましょう。
| 名称 | 方法 |
|---|---|
| 木酢液 | 園芸肥料としてホームセンターなどで販売されているものを希釈し、容器や皿に入れ猫の通路に設置します。スポンジや布に浸み込ませたものを皿に乗せると、効果が長期間持続します。 ・木酢液を使用した自家製ねこよけ秘薬の作り方 材料:木酢液(400ml)、レモンバームの葉(20から30枚)、唐辛子(10から15本) 作り方:(1)500mlのペットボトルの中に木酢液を8分目位まで入れます。 (2)その中にレモンバームの葉を手でよく揉んでから入れます。 (3)更に、細かくちぎった唐辛子を10本以上加えてください。 (4)そのままの状態で1から2日おいてから、レモンバームと唐辛子を取り除けば出来上がり。 使い方:4から8倍に薄めてから使います。匂いがきつい場合は10倍くらいまで薄めてもかまいません。 |
| 食用酢 | 木酢液と同様に使用します。臭いが相当きついため2から10倍程度に薄めて使用してください。 |
| 柑橘類 | みかんなどの柑橘類は猫が嫌う臭いを放っていると言われています。柑橘類の皮を撒く、あるいは柑橘類の香りのする薬品を置きます。 |
| 市販の猫よけ剤 | ペットショップや薬局、ホームセンター等で販売されているものを使います。 |
【注意】化学薬品などは化学物質過敏症など健康被害の誘因となる可能性があるので、使用に際してはご注意ください。
構造物による忌避方法
出入り口や猫が休息する場所、猫が塀を飛び越える時に足場になる場所などに、猫がいやがるものを置く方法です。
| 名称 | 方法 |
|---|---|
| トゲトゲのあるマット | ホームセンターや園芸用品売り場等で販売されているトゲトゲのあるマットを、塀の上や猫の侵入経路に設置します。 |
| ガムテープ | 脚の裏がベタッとなるので嫌がります。 |
| 卵の殻 | 乾燥して細かくしてばらまきます。 |
| テグス | 釣りのテグスを張り巡らせます。 |
| ネット | ネットを張った上に乗ると不安定で嫌がります。 |

物理的に追い払う方法
| 名称 | 方法 |
|---|---|
| 水を撒く | 猫は臭いに敏感で、以前に付けた自分の臭いのある場所で糞尿をします。水できれいに洗い流して臭いを消します。 |
| 超音波式猫回避装置 | センサーにより自動感知し、人の可聴域よりも高い周波数の音を発生させます。 【注意】超音波はほかの動物(犬など)や子どもなどの一部の方に聞こえるため、設置位置や方向には十分ご配慮ください。 |
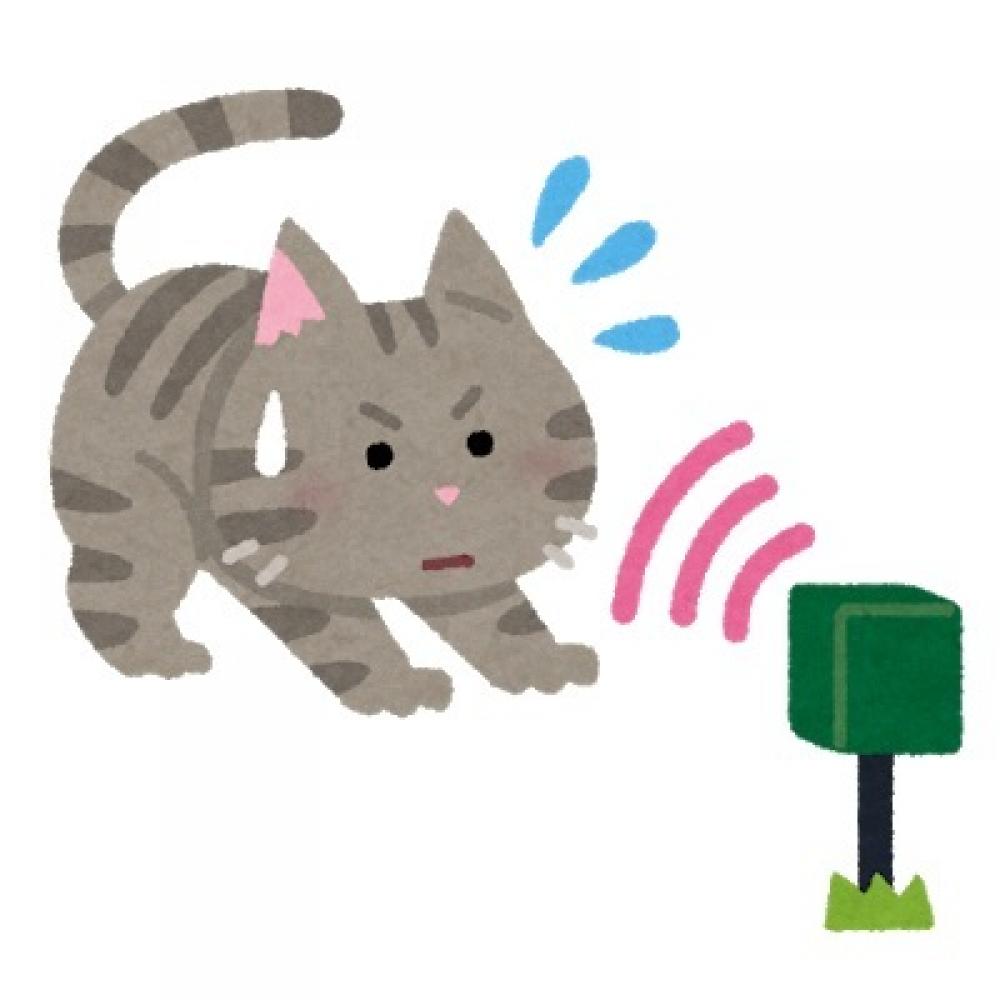
超音波式猫回避装置の貸し出しについて
東大阪市では、猫でお困りの方に対して超音波式猫回避装置の貸し出しを行っています。
貸し出し状況等により、順番待ちになることもありますので、事前に動物指導センターまでお問合せください。
【貸し出し条件】
- 貸し出しには、動物指導センター窓口での申請が必要です。
- 1人1機で、貸し出し期間は2週間です。
- 貸し出しを希望される方は、本人確認書類をご持参ください。
- 使用にあたっては、取扱い説明書の内容を理解した上で、自己の責任において使用・管理をお願いします。
【注意】本機はあくまでも試用を目的としたものであり、自衛策の方法を説明するために貸し出しするもので、一人でも多くの市民に貸し出しをするため、長期借用や複数回の借用はできません。
不妊去勢手術費用の助成について
猫の適正飼養の推進を図り、地域における猫の被害の軽減と不幸な命を増やさないため、東大阪市では市内で飼養もしくは生息する猫について、不妊去勢手術費用の一部を助成しています。詳しくは下記のページを参照ください。
地域猫活動について
地域猫活動とは、地域住民と飼い主のいない猫との共生をめざし、地域住民の合意を得て不妊去勢手術や管理を行ったり、新しい飼い主を捜して飼い猫にしていくことで、将来的に飼い主のいない猫をなくしていく取り組みのことです。詳しくは下記のページを参照ください。
