東大阪の"いまむかし"
生駒山のふもとから河内平野にひろがる東大阪市の歴史は、いまから数万年前、旧石器時代にはじまりました。
そのころ市域の大部分は、湿地で、山麓から当時の石器が見つかっています。つづく縄文・弥生・古墳時代には、市内は海から湖と湿地帯へと移りかわり、山麓を中心として100以上の集落や古墳がつくられたことが遺跡からわかります。
河内平野の開発も進み、国郡制が整えられた大化の改新以降は、河内郡衙(郡役所)が河内町、若江郡衙が若江周辺におかれていたと考えられます。奈良時代には生駒山のふもとの入江は「草香江」と呼ばれ、万葉集にも歌われています。
鎌倉時代にはいると、興法寺・慈光寺・神感寺などの山寺が真言宗の道場として栄え、南北朝時代に南朝方の拠点となりました。正平3年(1348年)、楠木正行は往生院に陣をおいて足利方と戦い、飯盛山で戦死しました。
室町時代には、河内国の争奪をめぐる争いがくり返され、河内国守護畠山氏の築いた若江城はその拠点となり、後には三好義継の居城となりました。
徳川家康が豊臣家を攻めた大坂冬・夏の陣では、若江が激戦の地となり、大坂方の武将・木村重成はここで戦死しました。

江戸時代、河内平野を南北に流れ、毎年のように洪水を繰り返していた大和川は、今米村・中甚兵衛らの幕府への請願が実を結び、宝永元年(1704年)堺までの付け替えが行われました。
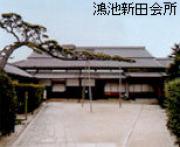
広い旧川床や池沼地は埋め立てられて新田となりました。大阪の豪商、鴻池善右衛門が開発した鴻池新田には、いまも豪壮な会所が残っています。

旧川床には木綿が栽培され、河内木綿の名が全国に広がりました。山麓地帯では、水車を利用したいくつかの地域産業が発達しました。
文化面でも松尾芭蕉が元禄7年(1694年)「菊の香にくらがり登る節句哉」の句を残し、日下に仮寓していた上田秋成が「山霧記」「鳴鶴園記」などの作品を残しました。ついで文化・文政の時代から幕末にかけ、国学、和歌、俳諧などを学ぶ庄屋層を中心とした多彩な河内文芸が醸成されたのです。
明治に入ると河内国は河内県・堺県などに変わったのち、明治14年(1881年)から大阪府となり、80近い村々も22年(1889年)の市町村制施行により、19村に統合、河内・若江・渋川の3国に分かれていた郡制も、29年(1896年)には中河内郡になりました。
農村の景観が商工業地域に変わってきたのは交通機関の発達です。明治22年(1889年)に大阪鉄道(いまのJR・関西線)、明治28年(1895年)には、浪速鉄道(いまのJR・学研都市線)が開通しました。大正3年(1914年)には私鉄最長の生駒トンネルが完成し、大阪電気軌道の大阪・上本町と奈良間(いまの近鉄奈良線)が開通、ついで大正13年(1924年)には布施―八尾間(いまの近鉄大阪線)が開通しました。

大正14年に町制を敷いた布施町と小阪町、昭和4年に町となった楠根町隣接の意岐部、長瀬、弥刀の3村を合わせて昭和12年4月に布施市が誕生しました。これが現在の西地区です。
生駒山ろくや平野の中央部にある現在の東地区は昭和30年1月に枚岡・縄手・石切の3町と孔舎衙村が合併して枚岡市が、同様に中地区は盾津・玉川の2町と英田・三野郷・若江の3村が合併して河内市が誕生しました。
現在、人生80年時代への対応や地域の特性をいかした個性あるまちづくりの推進、うるおいとやすらぎのある快適環境の創造、さらに、関西国際空港と関西文化学術研究都市の結節点に位置する東大阪新都心の整備などに積極的に取り組み、子どもからお年寄りまで、すべての市民が幸せに暮らせるまちづくりの実現をめざしています。
