児童手当制度
児童手当制度について
児童手当制度は、次代の社会を担う児童の健やかな成長を支援することを目的とし、児童を養育している父母その他の保護者に手当を支給する制度です。
現在の児童手当制度は、平成22年4月から平成24年3月までの「子ども手当」制度を引き継ぎ、平成24年4月より始まりました。
令和6年10月(令和6年12月支給分)より制度が改正されました。
児童手当制度
支給対象
東大阪市に居住し、高校生年代(18歳到達後最初の年度末)までの児童を養育している方(請求者は父母のうち、前年度の所得が高い方が該当します。)
- 公務員の方(独立行政法人・地方独立行政法人は除く)は勤務先へ請求してください。
- 外国籍の方も対象になります。(在留資格のない方、在留資格が「短期滞在」「興行」等の方は除きます。)
- 海外に住んでいる児童は対象外になります。(留学中の児童に関しては支給できる場合があります。)
- 離婚や離婚前提で父母が別居している場合は、児童と同居している方が優先的に手当を受給できます。(単身赴任等で別居後も父母が生計を同じくしている場合は除きます。)
- 児童が児童福祉施設等に入所している場合、施設の設置者等に支給されるため、保護者は受給できなくなります。
- 受給者がギャンブル依存症等で児童手当を児童の養育目的以外に使用している場合に受給者変更ができることがありますので、ご相談ください。
算定対象の子
児童手当の支給はありませんが、児童の人数に数えることができる方を「算定対象の子」としています。
算定対象の子として含められるのは、18歳に達する日以後の最初の3月31日をこえて、22歳に達する日以後の最初の3月31日までの子で、父母が監護しており、かつ生計費の負担をしている方です。
同居、別居に関わらず、父母が算定対象年齢の子を日常的に面倒を見ており、生活費や学費などを負担している場合は、その旨を申し立ていただくことによって対象人数に数えることができます。
ただし、対象年齢の子が自立し、父母による生活費等の負担がない場合は、算定対象となりませんのでご注意ください。
支給額
| 対象児童 | 支給月額 |
|---|---|
| 3歳未満の第1子・第2子 | 15,000円 |
| 3歳未満の第3子以降 | 30,000円 |
| 3歳から18歳の第1子・第2子 | 10,000円 |
| 3歳から18歳の第3子以降 | 30,000円 |
- 18歳の児童は18歳に達する日以後の最初の3月31日までの方が対象です(3月分まで支給となり、翌月の4月分から対象外となります)。
- 児童手当における第3子以降とは、22歳に到達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のうち、算定対象となっているお子様の年長者から第1子、第2子と数え、3人目以降の子をいいます。
支給時期
原則として、偶数月(2月・4月・6月・8月・10月・12月)の各15日に、それぞれの前月分までを指定された口座に振り込みます。
ただし15日が金融機関の休業日(土日祝)にあたる場合は、直前の営業日(平日)に振り込みとなります。
現況届(更新の手続き)
毎年6月に現況届の提出(更新の手続き)が必要でしたが、令和4年度から受給者の現況を公簿等で確認することで、現況届の提出が原則として不要となりました。
ただし、以下の方は引き続き現況届の提出が必要です。
- 配偶者からの暴力等により住民票の住所地が東大阪市と異なる方
- 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
- 離婚協議中で配偶者と別居されている方
- 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
- 加入年金が公簿で確認できない方
- 算定対象の子の職業が学生以外(無職やその他等)の方
- 算定対象の子の住民票が他市にある方
- その他、児童と別居している等で東大阪市から提出の案内があった方
現況届がご自宅に届いた方は提出していただきますよう、お願いします。
現況届の提出がないと、8月分以降の手当が停止されます。また、そのまま2年が経過すると、時効となり受給権がなくなりますので、必ず届け出てください。
児童手当の請求について
出生、転入、受給者変更などの場合で手当の支給を受けるためには、児童を養育している親等が住所地の市区町村に申請を行う必要があります。
公務員の方(独立行政法人・地方独立行政法人は除く)は勤務先へ請求してください。
支給開始月
児童手当の支給は、児童手当の受給者が認定請求した日の属する月の翌月分から始まり、児童手当の支給すべき事由が消滅した日の属する月分で終了します。
児童手当受給の事由が発生した日(児童の出生日、転入された場合の前住所地の転出予定日、公務員を退職した日または独立行政法人等へ出向された日等)が月末であっても、事由発生日の翌日より15日以内に請求を行えば事由発生日の属する月の翌月分より支給できます。
請求に必要なもの
- 請求者名義の金融機関の通帳(普通口座に限る)
- 請求者の健康保険証、資格確認書または資格情報のお知らせの写し
- 被用者年金加入証明書(請求者が「国家公務員共済」「地方公務員等共済」に加入している場合のみ)
- 請求者および配偶者のマイナンバー(個人番号)確認書類
- 児童のマイナンバー(個人番号)確認書類(単身赴任等で児童と別居になる場合のみ)
- 請求の際は、マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等での本人確認が必要です。
- 従来、最新年度の所得証明書および、単身赴任等で児童が市外に別居している場合は、児童が居住している世帯全員の住民票(続柄記載のもの)が必要でしたが、個人番号(マイナンバー)を届出書へ記載することにより、省略できるようになりました。
- このほか、状況に応じて他の書類が必要となる場合があります。
電子申請
東大阪市では令和3年10月から児童手当の申請を電子申請で行うことができるようになりました。電子申請が可能な手続きは以下のとおりです。
- 新規認定請求
- 額改定の認定請求及び届出
- 受給事由消滅の届出
- 住所・氏名変更の届出
- 口座変更の届出
- 監護相当・生計費の負担状況の届出(多子加算の申請・変更)
電子申請をするためには、
- マイナンバーカード
- パソコン端末またはスマートフォン端末
- ICカードリーダライタ(パソコン端末で手続きされる方のみ)
が必要です。
別途、申請内容により添付書類の提出を求める場合があります。
郵送で申請される方へ
里帰り出産などにより出生の翌日から起算して15日以内に窓口で申請できない場合、転入等により前住所地の転出予定日の翌日から起算して15日以内に窓口で申請できない場合は、郵送での受付も可能です。
ただし、郵送で申請される場合は、市役所に請求書が到着した日が申請日となります。
不着・遅延等の郵便事故について東大阪市は一切責任を負いませんのでご了承ください。特定記録郵便や書留郵便など、経過がわかる方法で郵送されることをお勧めします。なお、記入漏れ等にご注意ください。
振込先口座の変更
児童手当の振込先口座の変更を希望される場合は、口座変更届を提出してください。変更できる口座は、受給者本人名義の口座に限ります。配偶者、児童の口座には変更できません。
なお、公金受取口座の利用も可能です。児童手当の振込先として登録後、マイナポータル上で公金受取口座を変更すると、児童手当の振込先が自動的に変更されます。ただし、マイナポータル上の変更手続きの時期によっては、直近の児童手当の振込先に反映できない場合があります。
児童手当からの保育所(園)及び認定こども園保育料の特別徴収
保育料の収納対策の一環として、保育料の滞納が続く方を対象に児童手当からの特別徴収を市の歳入の確保と公平性の確保の観点から10月以降の偶数月に実施します。
対象となる方には、施設給付課から特別徴収予告通知書を、国民年金課から児童手当に係る保育料特別徴収通知書を送付します。
寄付
児童手当の全部または一部の支給を受けずに東大阪市の子育て支援事業のため活かして欲しいという方には、簡便に寄付を行うことができます。
ご関心のある方は、国民年金課にお問合せください。
震災、風水害、火災その他これに類する災害で被災された方へ
児童手当の認定請求等については、事実の発生した日(例えば出生の場合は出生日)の翌日より15日以内に手続きをしないと受付日の翌月からとなりますが、被災された方は「災害その他やむを得ない理由」として遡って認定することが可能です。
また、災害その他特別の事情がある場合において、特に必要があると認めるときは、請求書等に添えなければならない書類を省略、またはこれに替わる他の書類を添えて提出することができます。
(必要書類について)
- 本人確認ができる資料
- その他必要書類については、災害の程度によって個別に対応します。
備考:罹災証明書の提出が必要な場合があります。
こんなときは届出が必要です
- 子どもが生まれた(出生日の翌日より15日以内に手続きしてください)
- 受給者が市外から転入してきた(前住所地の転出予定日の翌日から15日以内に手続きしてください)
- 受給者、配偶者、児童、算定対象の子の住所が変更になった(世帯全員の市内転居で、公簿で住所変更が確認できる場合は届出不要)
- 受給者が公務員になった、公務員でなくなった
- 受給者、配偶者、児童、算定対象の子の氏名が変更になった
- 受給者、児童または算定対象の子が他の市区町村に転出する
- 児童または算定対象の子と別居した
- 児童が児童養護施設等に入所または退所した
- 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象児童がいなくなった
- 算定対象の子を監護または生計費の負担をしなくなった
- 支給対象児童数に増減があった
- 受給者や児童が死亡した
- 受給者や児童が拘禁、勾留された
- 受給者の加入する年金種別が変更になった(転職等で、年金の種別が変わらなければ手続きは不要)
- 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至った、または児童を養育していた配偶者を有しなくなった
- 離婚協議中の受給者が離婚をした
- 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けた など
(参考)令和6年10月からの児童手当法の改正について
制度改正の内容
1.支給対象児童を高校生年代まで延長
児童手当の支給対象児童が、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童(以下、「高校生年代」といいます。)に延長されます。
2.所得制限の撤廃
所得に関わらず、児童を養育する全世帯に児童手当が支給されます。
なお、児童手当の受給者は、現行制度のとおり児童を養育する父母のうち前年度の所得が高い方となります。
3.第3子以降としてカウントする対象児童の年齢の変更および第3子以降の支給額を増額
算定対象が、22歳に達する日以後の最初の3月31日までの子に延長されます。
また、第3子以降の支給額が3万円に増額となります。
4.支給月を年3回から年6回(偶数月)に変更
児童手当の支給月が年6回(2月、4月、6月、8月、10月、12月)に変更となり、それぞれ前月までの分を支給します。
| 改正前 (令和6年9月(令和6年10月支給)分まで) | 改正後 (令和6年10月(令和6年12月支給)分から) | |
|---|---|---|
| 支給対象児童 | 中学校修了まで (15歳に達する日以後の最初の3月31日まで) | 高校生年代まで (18歳に達する日以後の最初の3月31日まで) |
| 所得制限 | あり | なし |
| 算定対象児童 | 高校生年代まで | 22歳に達する日以後の最初の3月31日まで |
| 支給額 |
|
|
| 支払い回数 | 年3回 (2月、6月、10月) | 年6回 (2月、4月、6月、8月、10月、12月) |
制度改正による手続きは令和7年3月31日までに申請を受け付けした分は令和6年10月まで遡って支給します。手続きが令和7年4月1日以降になった場合は遡ることはできず、申請した翌月分からの支給となります。
お問い合わせ
東大阪市市民生活部国民年金課
電話: 06(4309)3165
ファクス: 06(4309)3805
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
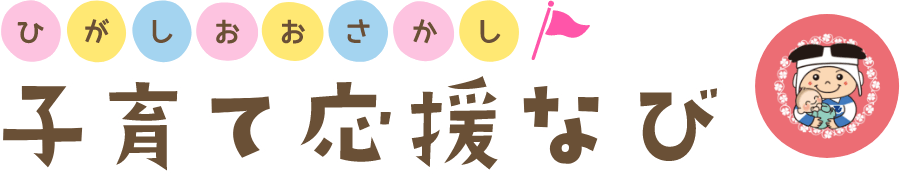
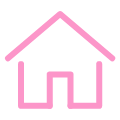 ホーム
ホーム 妊娠や出産・産後のこと
妊娠や出産・産後のこと 健診や予防接種
健診や予防接種 子どもを預けたい
子どもを預けたい 子どもと出かける
子どもと出かける 手当や助成
手当や助成 相談したい
相談したい