パンができるまで
給食のパンができるまで

東大阪市の学校給食のパンは、現在2つのパン屋さんが作っています。
そのうち地元東大阪市内に工場のある、業者さんにご協力いただき、給食のパンができるまでをご紹介します。
この日は、コッペパンを作っていました。
まだ外は暗い、朝の3時、4時頃から作業は始まります。
生地作り

<粉ふるい>
小麦粉は、まず『粉ふるい機』にかけられます。(原料から異物が入らないように)

ふるった粉は、パイプを通って、生地を作る『ミキサー』に送られます。
パンの製法にはいくつか種類がありますが、給食では『中種法』という製法でパンを作っています。小麦粉・水・イーストをこねて作った生地を5時間くらいねかせて中種とし、本仕込みの時に加えて、生地をつくります。しっかり醗酵したパンになります。

<ミキシング>
『ミキサー』では中種・小麦粉・水のほか、油脂(バターやショートニング)脱脂粉乳・砂糖などの材料を入れて約16分間こねます。

<発酵>
こねあがった生地をケースに分けて、約30分間、室温に置き<28℃位に調整されている>、発酵させます。

<発酵>
ケースの中で、2倍くらいにふくらみます。
分割・成形

<分割>
ふくらんだ生地は、左の『分割機』で同じ大きさに分けます。

<まるめ>
分割機で分けた後、『丸目機』でまるめます。ガイドにそって、すりばちがたのうつわの中を上がってくることで、きれいにまるまります。

<発酵>
まるめた生地は、約20分かけて
『プルファー』の中をとおり、さらに発酵させられます。

<成型>
成型機で、生地の形をととのえます。

<金属探知機によるチェック>
成型した生地は、金属探知機に通します。

鉄板にうちつけるようにして、並べていきます。コッペパンの時は鉄板1枚に8コならべます。うずまきパンなどの形を作るのも、このときに行います。

<ホイロ(発酵)>
生地を並べた鉄板をラックにおき、発酵室(『ホイロ』とよばれる)へ約45分間入れます。

きれいなコッペ型にふくらみます。
焼成

<焼成>
鉄板をオーブンへ入れていきます。

長いトンネルのようなオーブンの中を、コンベアでゆっくり流れていきます。
※焼く時間は9~12分くらいです。パンの種類、大きさによって温度や時間を設定します。

<焼き上がり>
オーブンを出るとちょうど焼き上がり!
おいしそうに焼けたパンが、次々に出てきます。

<冷却>
パンはアツアツのまま包装すると、水滴がつき、ベタついてしまうので、ラックでしばらく冷まします。

<目視点検>
包装するときは、パンの裏をチェックして、不良品がないか確認します。

<金属探知機によるチェック>
最後にもう一度金属探知機にかけます。

出来上がったパンは、トラックで各学校に運ばれます。
『いいパンを作るためにがんばっています。皆さんが「おいしい」と喜んで、たくさん食べてくれるとうれしいです。』と、おっしゃっていました。
皆さん給食のパンは好き嫌いせず、しっかり食べていますか?
お問い合わせ
東大阪市教育委員会事務局学校教育部学校給食課
電話: 06(4309)3276・06(4309)3277
ファクス: 06(4309)3867
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
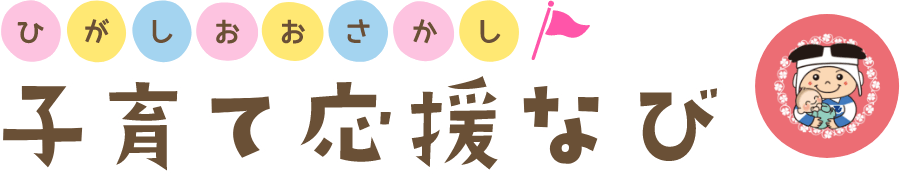
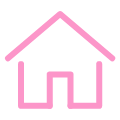 ホーム
ホーム 妊娠や出産・産後のこと
妊娠や出産・産後のこと 健診や予防接種
健診や予防接種 子どもを預けたい
子どもを預けたい 子どもと出かける
子どもと出かける 手当や助成
手当や助成 相談したい
相談したい