歯科医師からのメッセージ(3歳)

1歳から3歳のお子さんをもつあなたへ
3歳のころ
はじめに
子ども同士や保護者同士のお付き合いが広がることは、歓迎すべきでことです。ただ、ある保護者が「これくらいは普通だろう」と思っている間食の内容や回数が、歯からみるとちょっと好ましくない状況になっている場合も、中にはあるようです。
また、幼児の要求に引き摺られて、保護者の方が与える間食の回数が多くなるということもあるようです。判断力がまだ育っていない幼児は疑問もなく、それに馴染んでいくかもしれません。そうなると、歯はリスクに曝(さら)される機会が多くなり、その期間が長くなってくると、歯はむし歯に向かって変化していく危険性が高まります。

幼児歯科健診の結果の一端
東大阪市で「むし歯あり」の子どもは、例えば平成26年度に1歳6か月児健診を受けた幼児の場合、1.3%(他に、むし歯のハイリスクと思われる子どもが7.0%)だったのですが、その同じ子どもたちが2年後の同28年度の3歳児健診を受けたときには、「むし歯あり」が19.1%になっています。初めの頃は順調であっても、その後リスク要因の大きい生活習慣に変わってきている子どもが多い、ということになりそうです。初めの頃の、子どもの良い生活習慣が緩まないようにしていただくことが望まれます。
3歳児健診は、母子保健法に実施することが定められているもので、歯科でも疾病または異常の発見に加え、相談・指導を行う、とされています。東大阪市では、3歳6か月の年齢時に実施され、その前月に個別案内を郵送しますので届いたら、是非受診してください。
さて、歯に関して3歳代で寄せられることが多い質問の幾つかを考えてみましょう。
フッ素は塗った方が良いのですか
歯科診察を受けて、子どもの歯の状態が良ければ、2つの考え方があります。一つは、状態が良いのに加えて、効果があるとされるフッ素も更に重ねて利用したいというものです。(この場合は、歯科医院でフッ素塗布の相談をしてみてください。)もう一つは、状態が良いのであれば、薬物的物質は使いたくないというものです。賛否両論あって、一方が正しくて他方は間違いとは言いきれません。保護者の方に自由度があると言えるでしょう。
しかし、もう既に「むし歯あり」の場合は、歯科医院で治療を受け、その後のリスクを下げる手段の一つとして、フッ素塗布もして頂きましょう。また、むし歯はなくてもハイリスク状態である場合も、やはり歯科医院でフッ素塗布を受けて、リスクを下げることを考えましょう。
ただし、フッ素を塗っただけですべてOKという訳ではありません。歯を悪くしないためには、間食も含め食生活習慣上の注意や、セルフケアとしての歯みがき習慣の実行が最も大切です。
あまり噛まないように思います
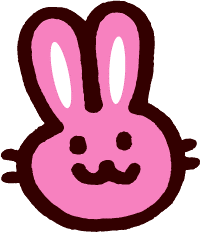
2つの場合があります。
・機能的に噛めない場合。
多数の歯にむし歯があったり、奥歯(乳臼歯)が揃っていなかったり、噛む経験が少なかったりすることが原因です。むし歯が沢山あるのであれば、歯科治療を受ける必要があります。奥歯がない、あるいは噛む力が不十分であるなら、調理形態を一旦、本人の噛める程度に戻して、ゆっくり練習していくことが求められます。
・噛もうとしない場合。
また、噛めないのではなく、噛む能力はあっても心理的な要因で、噛もうとしない子どももいます。実際には、こちらの場合の方が多いようです。この場合の最大の原因は、時刻は食事の時間なっていても、身体が命令する空腹感が来ていないような、生活サイクルになっていることです。幼児の昼食や夕食の1.5~2時間前は、液体も含めてカロリー(エネルギー)のを含むモノは与えず、本人の手の届かないようにしておくことで、解決するでしょう。食べるのが2時間くらい後になっても、身体が悪くなることはない、と割り切ることが必要かもしれません。
また稀には、「早く食べなさい」とか「もっと食べなさい」などの指示ばかりされていると、これも心理的に噛まない原因になることがある、と言われています。
幼児の要求に引き摺られるのではなく、食事時間に向けてお腹が空くようにしてあげ、また食事の雰囲気を落ち着いたものにしてあげてください。
上唇小帯が気になる
しかし、歯の仕上げみがきをしてあげる際には、上唇小帯が歯ブラシで擦られると子ども本人は痛いので、上の前歯は右半分・左半分に分けてみがいてあげてください。
また、お口の外側から外傷を受けた場合、上唇小帯が切れることが、稀にありますが、大きく切れて出血が酷い場合は縫いますが、傷口が小さい時は血が止まれば、そのままにしておきます。
ただ、ごく稀には、前歯が乳歯から大人の歯に生えかわった後も、まだ上唇小帯が歯の並びのウラ側の歯グキまでつながっている場合があります。この場合には手術をする可能性も考えられますが、その手術が必要なケースであるかどうか、3歳の時点で判定することは出来ません。

口臭がある
一方、身体が普通の状態であれば、お口の中には自然に唾液が出てきます。この唾液には抗菌作用があり、細菌の余分な繁殖を抑える働きをしてくれるので、細菌による臭いも許容範囲内に抑えられるのです。また、剥がれ落ちた粘膜やお口に幾らか残っている食べ物が腐敗する前であれば、物理的に洗い流す働きをしてくれるので、この点でも臭いを抑えてくれる訳です。
ところが、夜間の就眠中は長時間にわたって、唾液の分泌が少なく、上記の働きが劣勢で、そのあいだ細菌は仲間を増やすことが可能なので、朝起きてすぐの時は、口臭がしてもおかしくないのです。これは、ごく普通の生理的な口臭なので、問題はありません。
しかし、何らかの原因で体調がすぐれない時は、昼間であっても、元気な唾液が十分には出ないので、その働きが少なくなり、口臭がすることが多いようです。そういう時は、まず身体を本調子に戻してあげることが大切です。そのためには、早く布団に入れるようにして、回復力が発揮されるようにしてあげましょう。
そうしてみても、強い口臭が1週間や10日以上も続くような場合は、小児科の先生に診て頂き、対策を考えてください。


お問い合わせ
東大阪市役所 健康部 保健所東保健センター 電話: 072(982)2603 ファクス: 072(986)2135
中保健センター 電話: 072(965)6411 ファクス: 072(966)6527
西保健センター 電話: 06(6788)0085 ファクス: 06(6788)2916
母子保健・感染症課 電話: 072(970)5820 ファクス: 072(970)5821
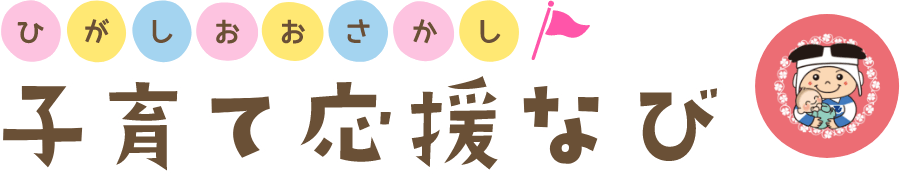
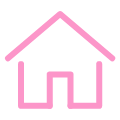 ホーム
ホーム 妊娠や出産・産後のこと
妊娠や出産・産後のこと 健診や予防接種
健診や予防接種 子どもを預けたい
子どもを預けたい 子どもと出かける
子どもと出かける 手当や助成
手当や助成 相談したい
相談したい