歯科医師からのメッセージ(生後11か月)

0歳から1歳までのお子さんをもつあなたへ
生後11か月のころ
赤ちゃんのお口の動き
一方、離乳については、口に入れた食べ物を、舌で口蓋(こうがい・口の天井にあたる部分)に押し付けてつぶす機能から、次の段階として、それではつぶせない程度の硬さの食べ物への対応が始まります。口の中で舌が左右に動いて食べ物を運んで、どこかでつぶそうとする動きが見られます。
離乳後期
まだ奥の歯グキで上手にすりつぶすことは難しいので、繊維質の強い生野菜や薄い海藻類、硬すぎる肉などは不適当かもしれません。また、硬いモノを包丁で細かく刻んでも、歯グキで擦りつぶすことは難しく、丸呑みを助長してしまうかもしれません。少しずつ硬さを増していくようにしましょう。
離乳後期のお口の管理・その1
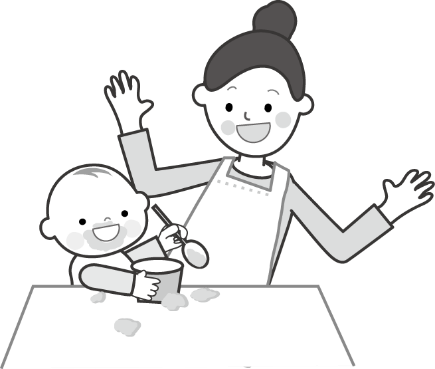
乳前歯が生えてきたら、歯みがきを考えたいのですが、この時期は、あくまで近い将来の「仕上げみがき」や「本人みがき」の準備の時期です。きょうの食べ物から歯を守るための作業、という意味合いは薄いと言っていいでしょう。離乳食は余程甘みに傾かない限り、それだけで歯を悪くする材料が殆んど含まれていないからです。(どの食べ物も同じように歯を悪くする訳ではありません。)
その方法ですが、いきなり歯をゴシゴシ擦ろうとすると、本人は歯みがきが大嫌いになってしまうようです。特に、上アゴの前歯は敏感なところで、その部分に強い刺激を受けることは、大変不愉快なことなのです。
大人の太ももの内側か、2つに折った座布団の上に子どもの頭を載せて、その大人の利き手でない方の手の指で子どもの唇をめくっておいて、上から歯が直視できる状態にして、大人の利き手で歯ブラシを持つようにしましょう。
歯グキに強く当たらないように、歯ブラシで簡単に触ってやることから始めましょう。歯ブラシに慣らしていくことがスタートです。
受け入れてくれるようになったら、子どもが安全な状態である時に、子どもの手の平に歯ブラシを置いてやりましょう。この時、歯ブラシの毛タバが親指の側に来るように置いてやってください。子どもが歯ブラシを自分でお口に持って行って、カミカミしてくれたら、これも自分みがきへの一つのステップです。
離乳後期のお口の管理・その2
というのは、眠っている間は唾液の分泌が相当程度少なくなるので、歯の表面を母乳やミルクで濡らしたままで寝入ると、唾液が歯を守ってくれる自然のシステムが活用されないことになるからです。母乳やミルクには乳糖が含まれており、砂糖ほどではありませんが、歯を溶かす酸が多少は作られる材料になることから、お口の中の環境を歯にとって不利なものにしている訳です。
味覚について
好きな食べ物だけでなく、幅広く栄養を摂取して健康に生きていくためには、味覚のトレーニングも必要と言えるでしょう。
よだれ
乳幼児健診では、「うちの子は、ヨダレが多いのですが大丈夫でしょうか?」という質問を受けることがあります。
唾液が多く作られていること自体は、健康であることの一つの結果ですから、何の問題もありません。しかし、お口に溜まった唾液を何気なく飲み込むという処理が、早くから上手くできる子どもから、それができるようになるまでそれなりの時間がかかる子どもまで、個人差が大きいようです。
誰でも同じことが同じ時期に身に付くとは限りません。遅めの子どもには、ヨダレ掛けを付け替えてあげるという、手間はかかるかもしれませんが、その子どもなりに学習してくれることを待ってあげましょう。
おしゃぶり

英語では「ダミー(dummy)」と呼ばれているのですが、乳首のダミー(模造品)ということのようです。
おしゃぶりを与えると、脈拍が安定し、泣く回数が減少し精神効果がみられる場合もあるので、すべて否定されるものではありません。
しかし、歯の列が形成されても、おしゃぶりが続いていて、その使用時間が長くなると、上の前歯の並びが乱れる場合があります。ただし、それが内科的な健康上の問題という訳ではありません。
「泣いてうるさいから」と簡単に与え続けるのではなく、お誕生を過ぎたら、おしゃぶりがないことに、少しずつでも慣れていってもらうようにしましょう。

お問い合わせ
東大阪市役所 健康部 保健所東保健センター 電話: 072(982)2603 ファクス: 072(986)2135
中保健センター 電話: 072(965)6411 ファクス: 072(966)6527
西保健センター 電話: 06(6788)0085 ファクス: 06(6788)2916
母子保健・感染症課 電話: 072(970)5820 ファクス: 072(970)5821
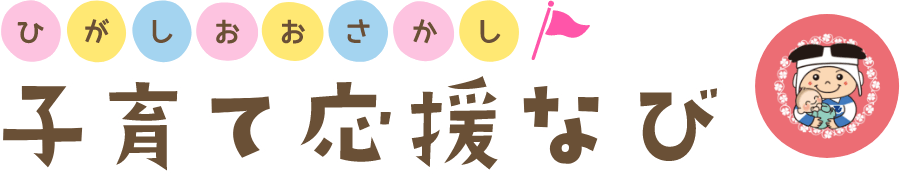
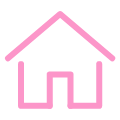 ホーム
ホーム 妊娠や出産・産後のこと
妊娠や出産・産後のこと 健診や予防接種
健診や予防接種 子どもを預けたい
子どもを預けたい 子どもと出かける
子どもと出かける 手当や助成
手当や助成 相談したい
相談したい