歯科医師からのメッセージ(1歳5か月)
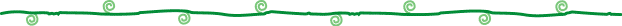
1歳から3歳のお子さんをもつあなたへ
1歳5か月のころ
健康診査について
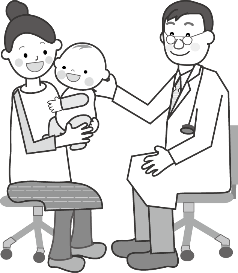
間もなく「1歳6か月児健診」の時期です。東大阪市でも、保健センターなどで実施されています。この健診は、母子保健法という法律に定められて実施されるもので、大切な健診です。
計測、医師・歯科医師による診察・保健指導、各種専門職による個別の保健指導などが行われます。
既に起こっている異常の発見だけでなく、考えられる疾患のリスク度を診て、ハイリスクであれば、保護者に注意を促し、日常生活の指導が行われることに価値があるのです。
歯科の健診って?
是非、歯科にも関心を持って、診察を受けてください。また、健診の前月に届く問診票に、日常生活や相談希望項目までしっかり記入して頂きますと、保護者の方の知りたいことの説明が行われやすくなりますので、活用してください。
コラム:実際に1歳6か月児の歯科健診を担当してきた歯科医師からのメッセージ
ここ二十数年間、多い頃には年間約4,500人、最近でも年間約3,500人の1歳6か月児のほとんどを、一人で歯科診察を行ってきた筆者の経験から、むし歯対策について、幾つかのことをお伝えしておきましょう。
(1)健診前の保護者の方の歯に関する記入事項と、実際の歯科診察の結果が相関していない場合も多いということ。
「子どもの歯をみがいてあげていますか」の問いに対する保護者の方の答え(自己申告)が「時々」や「いいえ」となっていても、実際に診察してみると、むし歯がないだけでなく、歯の表面の清潔度が高く、むし歯のリスクが感じられないという場合も多いのです。
歯みがき作業がむし歯予防のすべてなら、こんなことは起こらないはずです。つまり、むし歯の有無や歯の清潔度には、歯ブラシ以外にも大きな要因があると考えなければ説明がつかないのです。
(2)その要因とは、食生活の習慣と考えられます。
一つは、子どもの間食はどんなモノが多いか、という内容の問題です。大人の場合は、既に身体は出来上がっているので、間食は栄養的に必須のものではなく、気分転換や人との会話の機会などのように、精神的な部分が大きいのです。しかし、子どもの場合は、健康を維持し身体も成長していくために必要な栄養が、1日3回の食事だけでは摂取しきれないので、間食が必要なのです。
つまり、子どもの場合は間食といえども、お楽しみで食べるモノではなく、健康維持や成長に役立つ食べ物を提供してあげるのが正解です。お楽しみで食べるモノは、ともすれば製造段階で砂糖が加えてある場合も多いようです。これを材料にお口の中の菌類が酸や不溶性の粘着物質を沢山作りますので、お口の中の環境がそれだけで悪くなります。
一方、健康維持や成長に役立つ食べ物は、甘いモノであっても、その食品本来の甘味であり、酸の産生や粘着物質の形成は少ないので、歯は安全な場合が多いのです。
また、食生活の習慣には、食べる回数や食べるタイミングという要素も含まれます。糖の種類によって大きな差はあるのですが、糖類を含む食べ物がお口に入ると、それを材料に何がしかの酸が作られることになります。この酸が1回作られるとすぐにむし歯なるということではなく、自然に出てくる唾液が酸を和らげてくれる(中和作用)ので、安全な状態に戻ります。
また、酸が歯を溶かしかかっても、それが分子的レベルの範囲内の変化であれば、唾液が微細に補修してくれる(再石灰化作用)ので、これによっても歯は守られているのです。
ただし、これらの作用はその人なりの時間をかけて行われます。人によって唾液の力に強弱の差はありますが、最大の助けである唾液の力を活用するためには、食べてから次に食べるまでの時間の間隔を十分に取ることが必要です。間食の回数が3回以上であるとか、無計画にダラダラと与えているような場合は、唾液が歯を守ってくれる自然のシステムを使っていないことになるのです。
さらに、唾液の力という点では、短時間のお昼寝は別として、夜のお休みの直前にでも、何か食べるということになると、就眠中は長時間にわたって唾液の分泌が少ないので、この場合も唾液の力を活用していないことになります。
こうしたことから、子どものむし歯は、基本的に「食生活習慣病」の要素が強いと言えます。この食生活習慣の注意は、多くの場合は保護者も子どもも辛い歯ブラシ作業より行いやすく、歯だけでなく身体全体の健康維持にも役立つものです。
それは、歯ブラシで防げるむし歯もあるかもしれないからです。決して行わなくても良いということではありません。やっておいて損はないでしょう。
歯みがきについては、育児書にも母子健康手帳にも書かれており、確かに間違いではありません。それが難なくできるのであれば、実行した方が良いでしょう。ただ、今現在のむし歯対策という以上に、自分みがきの習慣づくりと考えるのが無難です。小学生期の後半頃から多くなる歯肉炎に始まる歯周病対策としてセルフケアが重要であることが分かっていますが、そのときに歯みがきの習慣や常識ができていなければ、歯周病の予防も治療も非常に困難なものになります。先を急ぐのではなく、幼児期からスタートして、ゆっくりと良い習慣を身に付けてあげて、その方法も上手になっていけば最高です。
健康診査のすすめ
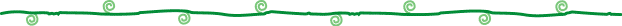
お問い合わせ
東大阪市役所 健康部 保健所東保健センター 電話: 072(982)2603 ファクス: 072(986)2135
中保健センター 電話: 072(965)6411 ファクス: 072(966)6527
西保健センター 電話: 06(6788)0085 ファクス: 06(6788)2916
母子保健・感染症課 電話: 072(970)5820 ファクス: 072(970)5821
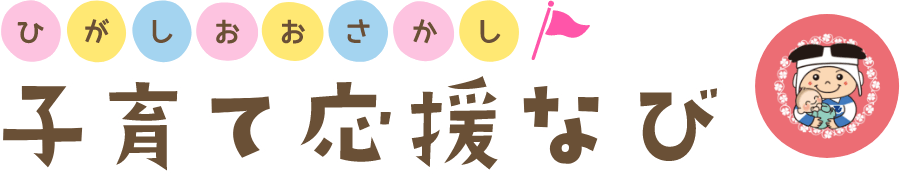
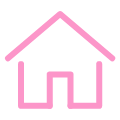 ホーム
ホーム 妊娠や出産・産後のこと
妊娠や出産・産後のこと 健診や予防接種
健診や予防接種 子どもを預けたい
子どもを預けたい 子どもと出かける
子どもと出かける 手当や助成
手当や助成 相談したい
相談したい